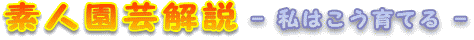園芸知識:日当たり
概要
- 多くの植物は、日光がないと光合成ができず、枯れてしまう。しかし、日光の要求量は、植物によってまちまちである。真夏の直射日光が平気な植物もあれば、真冬に窓越しの日光が当たっただけで葉が焼ける植物もある。全ての植物が直射日光を好むと思ったら大間違い。
- 直射日光を好み日陰を嫌う植物を「陽生植物(陽地生植物)」、半日陰~日陰を好み直射日光を嫌う植物を「陰生植物(陰地生植物)」という。
- ただ、「半日陰」という言葉は、今ひとつ定義がはっきりしない。目安としては、「午前中だけ直射日光が当たる場所」、もしくは「木漏れ日またはレースカーテン越しの日光が一日中当たる場所」をイメージするとよい。
- 陽生植物は、およそ5万ルクス以上の光を欲しがる。とはいえ、早朝から夕方まで一日中、日光浴が必要なわけではない。大抵は、一日に4~5時間当たれば足りる。植物によっては3時間程度でも大丈夫。
- 陽生植物の中には、「耐陰性(日光不足に耐える性質)」を備えたものがある。観葉植物がよい例で、ゴムノキやドラセナなどは、本来、熱帯の直射日光下で育つ木だが、室内の弱光下でも生きられる。が、耐陰性のある植物であっても、可能な限り強い日光に当てたほうが、葉色や花付きが良くなる。
- 陰生植物は、庭木のイヌマキのように直射日光下でも平気な植物と、アンスリウムのように短時間の直射日光さえ耐えられない植物に分かれる。前者は、栽培場所の選択の幅が広く、扱いやすいが、後者は、油断するとすぐに葉が焼けるので、少々やりにくい。なお後者は、自生地では森林の下草として生活している植物で、コケ類、シダ類、サトイモ科観葉植物、ラン科植物などに多い。3万ルクス以下の弱光を心がける。
- 建物の北側などは、日光が足りないため、植物の栽培に向かないと思われがち。が、陰生植物はもちろん、耐陰性の強い陽生植物も育てることができる。たとえ、一年中直射日光が当たらない場所であっても、育つ植物はたくさんあるので、最初からあきらめるのはよくない。
- 真夏の晴天時の日光は、10万ルクス以上といわれる。午後の西日は特に強烈で、どんな植物でも、当たるのを嫌がる。とはいえ、春以降、よく直射日光に当てて慣らしておけば、夏になっても、意外と葉焼けしないものである。
- 移動ができない地植えの植物は、真夏にしっかり水やりをし、葉の温度を下げるよう努めれば、葉焼け予防になる。
- 一般的に、葉が細長い・厚くて固い・垂直に立ち上がる、といった特徴を持つ植物は、強い日光を好む。逆に、葉が大きい、薄く柔らかい、水平方向に広がる、などの特徴を持つ植物は、弱い日光を好む。(もちろん例外はある。)
- 茎葉の表面にロウ状物質や粉状物質、短い毛を持つ植物は、強い日光に耐える傾向がある。ロウ状物質を持つ植物の例としてはナデシコやチューリップなどが、粉状物質を持つ植物には青葉系ギボウシなどがある。また、短毛を持つ植物(いわゆる「銀葉」「シルバーリーフ」)には、シロタエギクやシルバーレースなどがある。
- 観葉植物の中には、日光の量に応じ、葉色を変えたり、斑の大きさを変化させる種類がある。アレカヤシ、ネフロレピスの一部、ポトスなどがそうで、これらの植物は、葉の色柄を、好みで調節することが可能。
- 室内に飾るなどして、十分な日光が確保しにくければ、アルミ箔やアルミ蒸着フィルムを張った板を植物の後ろに置き、反射板の代わりにすれば、意外と明るくなる。
- 不幸にして葉焼けさせてしまうと、葉に、白や黒、淡褐色などをした、不規則な斑紋ができる。元に戻すことはできないので、そのまま放置し、患部が乾くまで待つ。よく乾いたらハサミなどで切り除く。このとき、生きた緑色の部分は、なるべく切らずに残す。病気ではないので、それ以上の処置は必要ない。
- 長期間遮光下にあった植物や、室内に置かれていた植物は、弱い光に慣れており、急に晴天の直射日光に当てると、高確率で葉焼けを起こす。最初は雨や曇りの日から始め、徐々に強い日光に慣らすようにする。また、直射日光に当てる時間を、最初の数日は30分とし、その後は1時間、2時間…というように、徐々に伸ばすのもよい方法である。
- 開花中の鉢植えを、室内の奥まった場所など、暗い場所に持ち込んで飾る場合は、3日を限度とする。耐陰性の強い植物なら一週間ほど置いても大丈夫だが、なるべく早く、明るい場所に戻すよう心がける。
- 日光を遮るには、専用の遮光用資材を用いる。園芸では、「寒冷紗」や「遮光ネット」がよく使われる。なお、昔ながらのよしずやすだれは、見た目には風情があるが、遮光率が高すぎて日光不足になるので避けたい。ただし、アンスリウムのように、かなりの日陰を好む植物には使える。
- 遮光用資材を植物体スレスレに張ると、風通しが悪くなったり、熱が籠もったりするので、少し距離を取る。最低でも50cm、できれば1m離したい。風で煽られやすいので、しっかりと固定する。
- 真夏に用いる遮光用資材は、黒または銀色のものが適する。黒色は特に遮光率が高い。銀色は熱を反射する効果もある。
- あまり強い遮光をしたくなければ、遮光率の低い白色を用いる。白い遮光用資材は、「強い日光を当てたいが、直射日光は嫌」という場合に最適である。
- 遮光用資材の代わりに、防寒用の「不織布」を使うのもよい。こちらの色は白と黒がある。
- 遮光用資材を二枚重ねると遮光率が上がる。たとえば50%の遮光材を二枚張ると、75%遮光される。(100%遮光ではない点に注意。一枚目で50%が遮光され、残りの50%が二枚目でさらに50%遮光されるので、75%が正解。)なお、二枚をぴったり重ねて張ると暗くなりすぎるので、50cm~1mくらいの間隔を取って張りたい。
- 植物には、夜の長さが一定時間より長くなると花芽を作る「短日植物」と、昼の長さが一定時間より長くなると花芽を作る「長日植物」、日の長さに関係なく、適した温度になれば花芽を作る「中性植物」がある。短日植物は秋~冬に開花する植物に多く、長日植物は春に開花する植物に多い。
- 短日植物を早く開花させるには、夜の暗黒状態を人為的に長くする「短日処理」を行う。この処理は、植物が蒸れないよう、真夏を避けて行うのが無難である。なお、いくつかの短日植物は、暗期(植物に光が当たらない時間帯)の長さだけでなく、「気温20℃以下」とか「10℃以下」などの別条件が加わるので注意。
- だいたい午後5時~翌朝8時くらいまで、植物にダンボール箱などをかぶせて暗黒状態にしておき、約1ヵ月~1ヵ月半、毎日続ける。(途中で一日くらい忘れても大丈夫らしいが、だからといって怠慢になるのは好ましくない。)小さな花芽が見えれば、作業は終了。一度花芽ができてしまえば、それ以降は、夜の長さに左右されなくなる。
- 短日植物は、新聞の文字が読める程度の光(5~10ルクス程度)があれば反応し、花芽ができなくなるので、夜でも明るい場所には置かない。外灯の当たる場所など、もってのほかである。
- 日光が射し込む角度(入射角度)は、6月21日頃の「夏至」の前後に最も高くなり、12月22日頃の「冬至」の前後に最も低くなる。この角度差は約46.8度とかなり大きく、夏至の頃は、強い日光がほぼ真上から降り注ぐ一方、冬至の頃は、日陰の範囲が大きく広がる。
- 日光の入射角度は、地域の緯度によって差がある。大阪市の場合、北緯を34.5度とすると、夏至が約79度、冬至が約32度、春分・秋分が約55.5度となる。
- また、太陽の出入りする位置は、夏至の頃に最も北寄りとなり、冬至の頃に最も南寄りとなる。
- なお、3月下旬の「春分」と、9月下旬の「秋分」の前後には、ほぼ真東と真西から太陽が出入りする。さらに、昼と夜の長さがほぼ一致する。
- 植物を育てる際は、こうした太陽の動きの変化を頭に入れておく必要がある。そうしないと、「春、北側の日陰に置いた観葉植物に、夏の直射日光が当たって葉を焼いた」とか、「夏、日当たりの良い場所に植えた庭木や多年草が、秋から春までずっと日陰になった」といった失敗をする。
- 日照時間の長さと、それに伴う気温の変動には、1ヵ月余りのズレがある。例えば、夏至は6月21日頃だが、最も気温が高くなるのは、それより約1ヵ月を経過した7月下旬~8月上旬頃である。同様に、冬至は12月22日頃に訪れるが、最も気温が低くなるのは1月下旬~2月上旬頃である。植物は、気温よりも、日照時間の変動(正確には夜の長さの変動)に従って生育し、動物よりも一足早く、季節の移ろいを感じている。上記のような短日処理が可能なのは、そのためである。